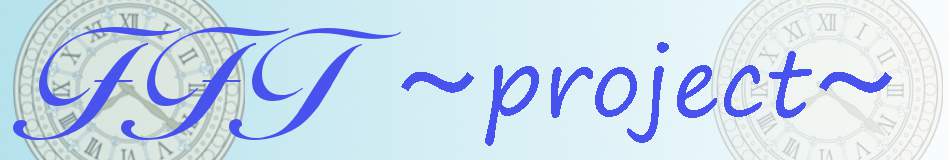H26 PM2問題
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2014h26_1/2014h26h_es_pm2_qs.pdf
H26 PM2解答
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2014h26_1/2014h26h_es_pm2_ans.pdf
H26 PM2講評
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2014h26_1/2014h26h_es_pm2_cmnt.pdf
問1 安全運転支援システム
設問1
(1)
(解説)
「DSSのサービスのうち一つを利用して」とあるので、表1を確認してみます。
3つのサービスの内容を確認してみると「道路上に侵入」に関係ありそうなものは決まりますね。
「走行車両情報提供サービス」にかかれている情報で良さそうです。
(解答)
位置、速度、移動方向
(2)
(解説)
「RTBの送信は省略している」と書いてあるので、経路に関する通信は不要ですね。
とはいえ、本文見てもまともな通信方法は書いていません。
この問題文と図7から推定していくしかないですね。
「各局は非同期に送信を開始する~車載局Cも同様の動作を行う」が通信動作の説明に
なります。
図7から、最初の3回の送信を見てみましょう
車載局AからA1を車載局Bに送信
車載局BからB1+A1を車載局AとCに送信
車載局CからC1+B1+A1を車載局Bに送信
ここから、”自局の情報+他局の情報”の順番でパケットが作成されることがわかりますね。
(a)を確認してみます。
車載局Aが受信するのは車載局Bが送信しないといけませんので、図7で言うところの
送信2回目、5回目、8回目のいずれかで受信できることになります。
送信2回目では、まだ車載局Cのパケットは含まれていませんので除外できます。
送信5回目は問題用に空欄aとなっていますので、その次の車載局Cの通信に着目します。
そこにはC2+B2+A2と書かれていますので、車載局Cは直前の車載局Bからのパケットを
受け取ったことになります。ここのA2に注目すると、車載局Aが送信したA2+B1を受信して
いる事がわかりますので、送信5回目の車載局Bは車載局Cからの情報を送信している
ことが判断できます。なので、車載局Aが2回目の送信した直後の車載局Bからの送信で
C1のパケットを受信していると言えそうです。
(b)を確認してみます。
空欄aは、車載局Bが2回目の送信なので、最初にB2が送信されます。
そのあとには、送信6回目を見るとA2が送られているので、A2も車載局Bから
送信されていることがわかります。車載局CはC1しか送信していませんのでC1も
車載局Bは送ることになります。あとはC1とA2の順番です。
(いろいろと考えて順番間違えましたが)
送信8回目の送信局Bのパケットを見てみましょう。B+C+Aの順番です、その前の送信も
送信局C、A、Bとなっており送信5回目と同じですね。なのでB+C+Aの順番で良さそうです。
空欄bは、送信5回目の車載局Bからの情報をもとに送信することになります。
車載局Aは3回目なのでA3を付与します。車載局Bからの情報しか受信しないので
次に来るのがB2+C1の順序となります。
(解答)
(a)2回目
(b)(空欄a)B2+C1+A1
(空欄b)A3+B2+C1
(3)
(解説)
「身元のほかに」とありましたので、「情報の改ざん」が頭に浮かんでくるようにしましょう。
(解答例)
障害物情報にデータの改ざんが無いこと
設問2
(1)
(解説)
(a)cですが、車載局Aと車載局Dの距離は40mとなり直接リンク可能ですのでホップ数が0となります。
車載局Cの経路有効時間から、考えましょう。
(問題文を読みなおしてもいいんでしょうが、表4に全部反映されているはずなので)
車載局Bと車載局Cの距離は20mです。1秒後は-10m、2秒後は-40m、3秒後は-70m(範囲外)
の時に経路有効時間は2秒となっていますので、同じように考えましょう。
車載局Bと車載局Dの距離は45m、1秒後は15m、2秒後は-15m、3秒後は-45m、
4秒後は-75m(範囲外)なので3秒ですね。
eは距離75m(範囲外)なので車載局Dを経由する必要かあります。なのでホップ数は1です。
車載局Bと車載局Eの距離は75m、1秒後は50m、2秒後は25m、3秒後は0m、4秒後は-25m、
5秒後は-50mなので5秒としたいのですが、現段階では「ホップ数1(車載局D)」の状態なので
車載局Dの3秒に律速されることとなります。
(解答)
c:0
d:3
e:1
f:3
(2)
(解説)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
0秒後 ()は経由局を示す A--20m--B----50m----- C--25m--D--25m--E 1秒後 A--20m--B--20m-- C--25m--D--30m--E 2秒後 A--20m--B 10m(C-B間) C--25m--D---35m---E 3秒後 A--20m--B 40m(C-B間)、15m(B-D間) C--25m--D---40m---E 4秒後 A--20m--B 70m(C-B間)、45m(B-D間) C--25m--(D)---45m---E 5秒後 A--20m--B 100m(C-B間)、75m(B-D間) C--25m--(D)---50m---(E) |
3秒後まで直接リンクできます。4秒後だとDを経由して通信が可能です。
5秒後だとE、Dを経由して通信が可能です。
6秒後だとD-E間が55m、A-D間85mと通信できません。
(解答)
5秒後
B→E→D→C
(3)
(解説)
(a)設問文、表5、図10を確認しながら解いていきましょう。
停止を検出するには「2回連続して同一車両位置」を検出する必要があります。
MP-C—MP-C—MP-C— (M:測定、P:処理、C:送信)
*1 *2 *3 (図10のイメージです)
車両停止と*1の測定が同時だと考えます。
同時は「どっちか分からないから悪い方向とする」は制御の基本です
なのだ*1では車両が同時刻に停止したにも関わらず車両の検出はしていないという
判定をしないといけません。*2、*3で停止を検出したとすると
*1~*3の処理が完了するまでが停止を検出する時間となります。
500ミリ秒+500ミリ秒+0.1ミリ秒が解となります。
(b)路側センサが演算完了~路上局が送信するまで
なので(考え方はaと同じです)
路側センサの送信処理+路上局のスキャン周期+路上局の処理時間+路上局の送信処理
で計算すればよいので
20 + 1000 + 0.1 + 20 = 1040.1ミリ秒
(c)これも図10のイメージで簡単に計算できます。
車載局の処理時間+車載局の送信時間+カーナビの処理時間
なので
0.05 + 1 + 200 = 201.05ミリ秒
設問の通りに小数第2位を四捨五入すると201.1ミリ秒
(解答)
(a) 1000.1ミリ秒
(b) 1000.1ミリ秒
(c) 201.1ミリ秒
設問3
(1)
(解説)
(a)路車間と車車間の大きな違いが解答になりそうです。
表2と表3を確認しましょう。特性の欄を見ると書いてありますね。
路車間は電波到達距離が広く、車車間は電波到達距離が狭い。
ここを使用して回答しましょう。
路上局が(問題文P3)「見通しが悪い交差点及びカーブ付近に設置されている」と
ありますのでこのキーワードも使用しましょう。
(b)
g 前問と同じですね、「電波到達範囲」で良さそうです。
h ここも表2から回答できます。特性欄に「相互干渉する可能性がある」と書いて
ありますので、これを使用しましょう
i 走行車両情報提供サービスは、現在「車車間通信」で実現しています。これを、
拡張しようという話なので「路車間通信」でよいでしょう。
j ここは現在の方式を書いておけば良さそうです。
(解答例)
(a) 見通しが悪い交差点及びカーブ付近で電波到達範囲が広がる
(b) g 電波到達範囲
h 相互干渉
i 車車間通信
j 路車間通信
(2)
(解説)
電波到達範囲が広いので、いろんな路上局の情報を受け取る可能性がありますね。
・反対車線の路上局
・交差点で付近で進行方向とは違う場所に設置されている
このあたりから解を作ってみるとよいでしょう。
また識別する方法ですが、ぱっと思い出したのは、
問題P5に「すべて固有の局番号を持つ」
問題P6に「設置位置情報が設定してある」
と書かれていたので、情報を送信してきた路上局の位置は確認できるはずです。
この位置情報と現在位置を利用すれば、進行方向の情報を利用できると考えられます。
(解答例)
理由:反対車線の路上局を受信した
交差点で進行方向と違う路上局から受信した
識別方法:車両の現在位置と移動方向から、進行方向に位置する局番号の
路上局からのみ情報を受信する
(3)
(解説)
「RTBが破棄される」理由は一つのみです。問題P7に「1秒未満になったら破棄する」とあります。
どんな時にこの条件を満たすか考えてみましょう。
渋滞なので、いろんな車両が加速と減速を繰り返しています。
ここで自車両が減速(停止)し、通信相手の車両が加速すると、相対速度は大きくなります。
そういう場合は、破棄条件に当てはまる場合が出てくるかもしれません。そこをまとめましょう。
対策は分かりませんでした。「速度を平均化する」「速度に応じて通知の周期を長くする」など
いろいろと考えたのですが、標準解答には到達しませんでした。
「破棄する前にリンク有効時間を再計算する」って、タイミングの問題ですよ。改善も改悪も
ありそうですが。。。皆さんはどう感じるでしょうか?
(解答例)
原因:自車と通信相手車両の相対速度から、リンク有効時間が1秒未満と推定され、RTBから破棄された
対策:渋滞時は自車と通信相手の相対速度の平均でリンク有効時間を計算する (本解答は推奨しません)